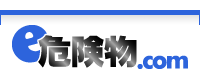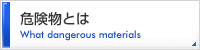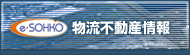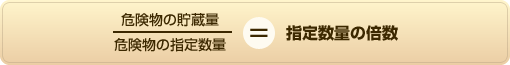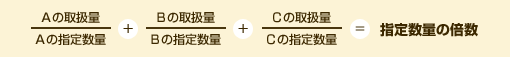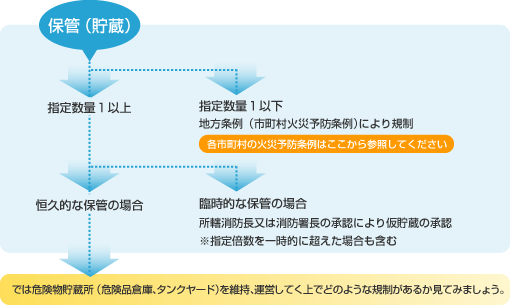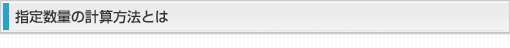
同一の場所で1つの危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合貯蔵し又は取り扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割り算した数値がその場所で貯蔵し、又は取り扱う危険物の指定数量の倍数になります。
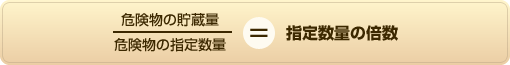
同一の場所で2つ以上危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合でも貯蔵又は取り扱うそれぞれの危険物の数量を それぞれの危険物の指定数量で割り算した数値の合計がその場所で貯蔵し、又は取り扱う危険物の指定数量の倍数になります。
例えば同一の貯蔵所でA、B、Cの危険物を取り扱っている場合
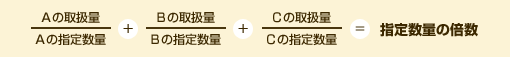
該当危険物に対する指定数量については、危険物とはの表を参照して下さい。
指定数量の計算の仕方がわかったところで消防法による危険物保管の規制を見ていきましょう。
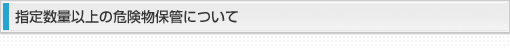
消防法第10条第1項において指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いについて、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し 又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されています。
ただし、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し 又は取り扱うことが出来るとされています。
※ここでいう指定数量以上とは指定数量の倍数が1以上のことを指します。
そこで指定数量の倍数が1以上か以下か下記のようなフローに分かれます。
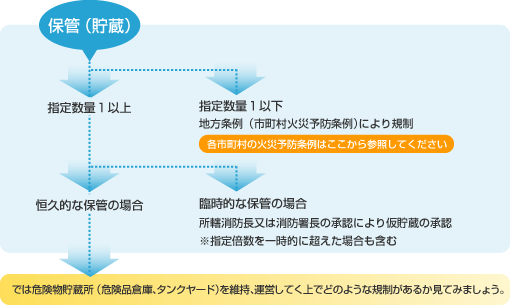
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設は大きく三つに区分されます。
製造所
|
危険物を製造する施設 |
| 貯蔵所 |
危険物を大きい指定倍数で扱う施設
(タンクターミナル保管、危険物倉庫、タンクローリー etc) |
| 取扱所 |
危険物を小さい指定倍数で扱う施設
(ガソリンスタンド、灯油、車のオイル等の販売店、車の整備工場 etc) |
当然危険物を大きい指定倍数で扱う施設である貯蔵所については安全を確保する為、さまざまな規制があります。
貯蔵・取扱の危険物の種類数量の各種届出の申請義務
位置・構造・設備の技術上の基準の遵守義務
危険物取扱者(有資格者)による取扱(立会い)義務
危険物保安監督者の選任義務
定期点検の実施義務
保安検査の受検義務
予防規程の作成義務
施設保安員・保安統括管理者の選任義務
指定倍数に合わせた保有空地の確保
避雷針の設置
標識、掲示板の設置
消化設備の設置
危険物以外の物品と同時貯蔵は出来ない。 |
|